CATEGORY : ヘルスケア |冷え症
月よみ薬膳師が教える! 冷えを癒して温める。「お茶とお灸」で始める温熱ケア術

一般社団法人日本フェムテック協会(以下、日本フェムテック協会)が、フェムテックやフェムテラシーをテーマにした「ランチタイムウェビナー」を毎週火曜12:00~12:30に定例開催中。今回は、そのアーカイブの中から、「お茶とお灸で始める冬の温熱ケア」をピックアップ。日本フェムテック協会の幹事 社会保険労務士の小口彩子さんを進行役に、鍼灸師で月よみ薬膳師の朝岡せんさんにお話していただきます。
Contents 目次
鍼灸師で月よみ薬膳の専門家、朝岡せんさんに教わる「冬の温熱ケア」

小口さん:みなさん、こんにちは。今日は、「お茶とお灸で始める冬の温熱ケア」ということで、鍼灸師で月よみ薬膳の専門家、朝岡せんさんに来ていただきました。よろしくお願いします。

朝岡さん:私はニューヨーク生まれ、名古屋育ちです。今も名古屋におります。肩書きがいろいろあるのですが、私が今の仕事(この道)についたきっかけは、子どもが生まれて自分で料理を提供する立場になったときに、食材選びやメニュー選びで家族の健康を左右するんだなって、すごい当たり前のことを身をもって実感したのがひとつ目の理由です。
もうひとつは、また仕事を始めようと思ったときに、子どもと一緒に料理教室がやれたら楽しいなと思ったことです。そこから野菜ソムリエの資格取得のために勉強をスタートしたのが始まりです。同時に、薬膳の資格取得も進めていました。

野菜ソムリエの資格取得時に、事務局の人から野菜教室をやってくださいと言われて、「野菜と薬膳」というテーマで教室を開催しました。その後、料理教室やケータリングのお話をいただいたり、カフェで月1回の薬膳ランチを提供させてもらったり、お弁当を作ったり、満月に合わせてイベントを開催するなど、18年くらい続けてきました。
小口さん:月よみ薬膳に関してはいかがですか。
朝岡さん:月よみは別の先生に習いました。女性の心と体のリズムって、月の満月、新月という移り変わっていくリズムとリンクしてるところがあるんです。生理周期が28日であるとか、満月・新月の前になると頭痛や体調が不安定になる人が少なからずいらっしゃると思うんです。私も毎回ではないけど、たまにあるんですよね。
女性の生理周期(女性のリズム)と月の移り変わり周期(月のリズム)に注目して、月のリズムに合わせて薬膳をとっていく「月よみ薬膳」の活動をしています。
小口さん:その中で、漢方という言葉をよく聞くし使うのですが、あらためて漢方について教えてください。
漢方についての基礎知識
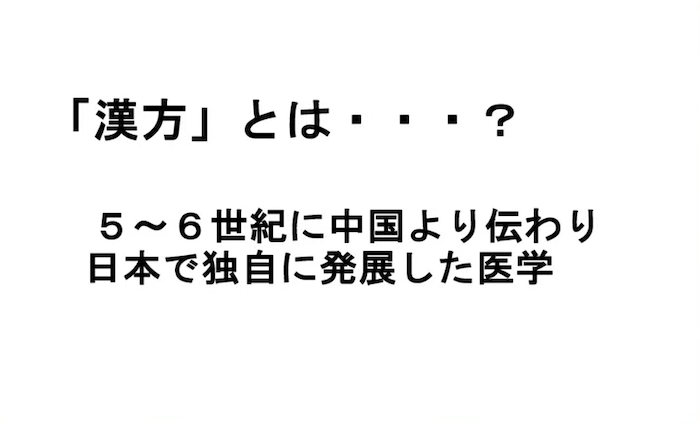
朝岡さん:西洋医学(蘭方)と真逆にあるものが漢方となります。歴史は西洋医学よりも古くて、5~6世紀ころに中国より伝わって、日本で独自に発展した医学です。ベースは中国医学です。
「漢方」の中には、漢方薬があり生薬と呼んだりもします。あとは鍼灸、私も鍼灸師です。マッサージと言われているものはあん摩というもので、「あん摩マッサージ、指圧」と呼ばれています。あとは「気功」があります。いろいろあるのですが、それぞれ役割や得意分野が異なります。
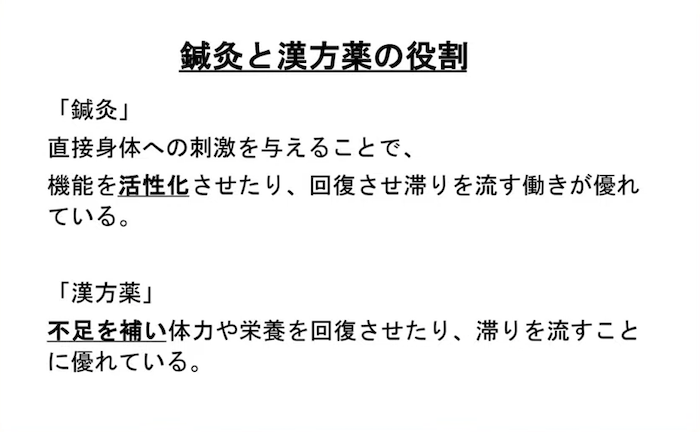
漢方薬は、口からとり入れることができる滋養があるもの。滞りがあれば流していくとか、デトックス効果があったり、内容によって役割があります。
鍼灸は、直接体に刺激を与えていくもの。日本で使ってる針は、髪の毛ぐらいの細い針を使用し、体に刺すので痛くないようにやるのがプロの技。
あと、お灸を使います。お灸は元々民間療法で、一般の人たちが自分たちで据えられるものなんです。誰でも買うことができるのがいいところ。
でも、だんだんと西洋医学の分野が大きくなっていて、以前より使う人が少なくなっているので残念です。自分でケアするのにいろんな効果をもたらしてくれるすばらしいアイテムだと思っております。
体の外から刺激を与えることと、体の内側から滋養を与えるので、巡りをよくしていく2つのことが相乗効果として存在しています。なので、ひとつより両方やったほうがより効果的と言われていますね。
小口さん:それぞれの役割分担をうまく補い合うこと、使い合わせることでより効果が出てくるということですね。ドラッグストアに行くといろいろな種類があるのでどれを選んだらいいのか悩んでたりしますよね。相談ができる人がいるといいなと思います。
朝岡さん:そうですね。鍼灸もですけども、漢方薬もその症状に合ってないと体にヒットしないというか…。なので、見極めがとても大切なのだけど、一度飲んでみてどうだったみたいなところはありますよね。漢方薬局や漢方医の先生のところに行かれても、まずこれ飲んでみてダメだったら次はこれにしよう、ってことになると思うので、長期目線で考えていかないといけないものになりますね。
小口さん:薬膳は漢方の一歩手前みたいな感じでとり入れたらいいんでしょうか。
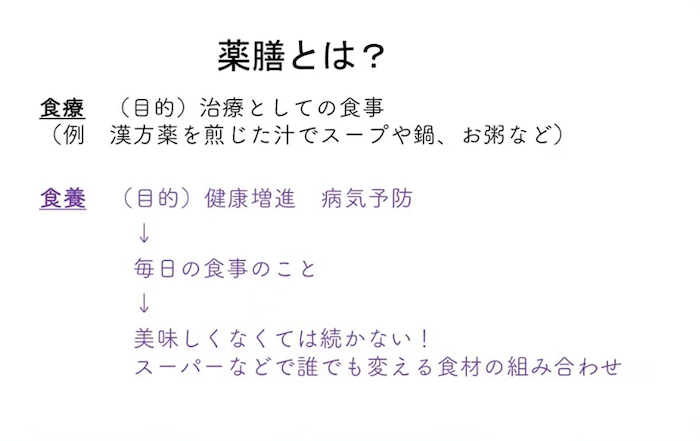
朝岡さん:はい、おっしゃる通りで、薬膳には2パターンの考え方があります。
「食療」は、食事の療法という役割があります。これは治療としての食事なので、漢方薬を煎じてスープを作ったり、お鍋やお粥にします。みなさんが持たれている薬膳のイメージは苦い・まずいなどがあると思うんですけど、この場合の薬膳はやはり食べにくいものもあります。
私が伝えている薬膳では、「食養」を伝えています。食事の養生のことです。目的は健康の増進や病気の予防に役立つ毎日の食事のこと。未病の段階で行う食事の養生のことです。
しかし薬膳と言ってもおいしくないと続きません。まずはおいしいことが前提です。また、スーパーなどで誰でも手に入る食材を組み合わせていくことも大切なポイントです。
小口さん:未病の段階で使う食養ってことですね。

朝岡さん:そうですね。じゃあ漢方薬と普通の食材とどう違うのか。いわゆる生薬といわれるものは漢方薬を構成するひとつひとつの材料です。私たちが普通にスーパーで買える食材には、生薬でもあり食材でもあるものがいっぱいあるんです。(資料は一例です)
例えば、シソやクコの実、しょうが、黒豆、ミントなどはじつは漢方薬のひとつ(生薬)としてとり入れたりするときもあります。体にとって効果が高い食材が身近にあるので、そういったものをうまく組み合わせて、自分の不調に適用させていくのが薬膳の役割と言ってもよいかもしれないですね。
冬におすすめのお茶とツボ

小口さん:では、実際にとり入れる方法を教えてください。今の時期にどんなのがおすすめとかあります。
朝岡さん:これから冬の季節に入るので、「冬のお灸とお茶」をご紹介します。
資料の左側(温性)は、体を温める働きがあるものです。茶葉の中だと紅茶がおすすめ。ちなみに体を冷やすお茶は「緑茶」で夏におすすめのお茶です。
あとはしょうがです。しょうがやシナモンを体にとり入れると体を温めます。紅茶にしょうがやシナモンを入れるとより温活効果が高まります。
また、手先足先の末端冷え性の人には、シナモンはとてもおすすめです。
しょうがは胃腸を温めると言われてますので、お腹の冷えが気になる人はしょうがを。末端冷え性の人はシナモン、みたいな感じで使い分けていただいてもいいかなと思います。あまり見かけないかもしれませんが、中国ローズのマイカイカやみかんの皮を干した陳皮なども温める素材です。
あと、資料右側の気血の巡りをよくすることも重要です。血流をよくすることで、体温が上がりますのでとても大事です。ローズマリーとかベニバナなどのハーブやしそ茶とか。ジャスミンやカモミールなども気血の巡りをよくします。
小口さん:ジャスミンやカモミールにも巡りをよくする効果があるんですね。香りがいいだけじゃないんですね。
朝岡さん:香りこそ大事です。考え方として、香りを嗅ぐことで気が巡って、血流もよくなっていきます。
小口さん:なるほど。お灸のお話が出てきたので、ツボについても教えてください。
朝岡さん:はい。冬におすすめのツボ4つを紹介します。
腎兪(ジンユ):ウエストラインのいちばんくびれている高さで背骨から指1本分外側の左右両側です。腰に手を当てたときに親指が自然に届くあたりが目印です。
湧泉(ユウセン):足の裏の中央よりやや上、足の指を曲げたときに最もくぼむ場所にあります。
三陰交(サンインコウ):内くるぶしの頂点から指4本分(親指以外の4指)ほど上の、すねの骨のすぐうしろのくぼみにあります。
太渓(タイケイ):足の内くるぶしとアキレス腱の間にあるくぼみにあります。
左右の腎兪の真ん中である背骨の真上にある命門(メイモン)というツボがあります。なのでその腎兪の並びにカイロをペタっと貼るだけでも冬のケアになります。冷えやこりをお持ちの人もここを温めていくといいですね。ピンポイントで当てなくてもなんとなくこの辺でも大丈夫。ツボは、六臓六腑の気の通り道が全身に12本走っているんですけど、その通り道のところにある「気」が出入りしているポイントです。
小口さん:なるほど。じゃあ、割と気楽に考えてトライしてみたらいいんですね。自分で刺激するときに何からやったらいいのかな、やりやすい方法ってありますか。

朝岡さん:例えば、これは「せんねん灸」というメーカーが出している火を使わないお灸です。カイロの要領でシールをはがすと熱が出てくるものです。中にヨモギが入っていて、シールで直接皮ふに貼ることができます。2~3時間の熱が持続します。熱と言っても、カイロのように43度くらいの温かさです。
女性のツボと言われる足の内くるぶしの指4本分上にある骨のキワの三陰交に貼ってみていただくのがおすすめ。お灸がなければ、ドライヤーや指圧で押すだけでもいいです。
小口さん:足元だと背中よりも手が届くので、自分でも簡単にできそうです。

朝岡さん:もう少しレベルアップしたい、チャレンジしたいなと思われたら、火をつけるタイプのお灸もあります。火を使うタイプはハードルがあるかもしれませんが、実際に火が入って熱が入ってくのには1分もかからないので、火をつけてからトータルで3分ほどで終わるお灸になります。
小口さん:自分で手軽にできるお灸は、調子の悪いときだけにするほうがいいのか、続けるほうがいいのか、どう考えたらいいですか。
朝岡さん:もちろん治療として使えるものなので、かゆみとか痛みに直接お灸を使っていくときもありますし、養生として毎日1回でも2回でも続けていただくことによって、体のメンテナンスにもなります。本当に幅広く使えるのでおすすめです。
小口さん:今までお灸を使ったことがないので、怖いとか熱いなどのイメージがあったのですが、気軽に試せそうなのでトライしてみて、体を温めながら寒い冬、年末年始を乗り越えていければと思います。
※本記事の内容は、2023年11月に配信された内容です。最新情報は公式サイトよりご確認お願いします。
【登壇者】※2024年12月時点
朝岡 せん 太洋商工株式会社 灸膳 鍼灸師 月よみ薬膳師
小口 彩子 日本フェムテック協会 幹事 社会保険労務士
【クレジット/協力】
一般社団法人 日本フェムテック協会 スペシャルコンテンツ
https://j-femtech.com/special_contents/
5万人が受講! 5分で無料。フェムテック認定資格3級はこちらから
>>>https://j-femtech.com/femcare-l/certificate/l3/FYTTE
文/FYTTE編集部





