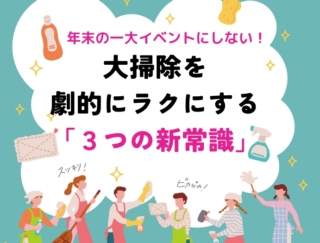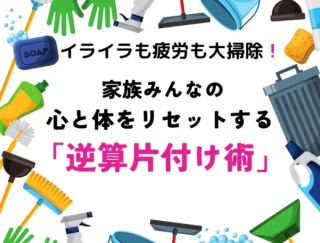人生100年時代と言われる現代は、自分はもちろん自分の親世代の健康状態とも向き合っていく必要があります(*FYTTEでは、「親子ウェルビーイング」と定義)。今回は、Dクリニックが提供するアルツハイマー診断ドックの監修を行っている順天堂大学脳神経外科 主任教授 近藤聡英先生と、お笑い芸人でエッセイストの、にしおかすみこさんによるスペシャルトークイベントより、「認知症」との向き合い方をお届けします。
Contents 目次
認知症の母の“見守り”を行う、にしおかすみこさんが登壇
認知症をテーマにしたトークショー「スペシャルトークイベント~自分と家族の未来のために~にしおかすみこさんと学ぶ認知症の最前線」に登壇した、にしおかすみこさん。イベント冒頭のあいさつで、
「にしおかすみこだよ。イベントに来て浮かれている2007年の一発屋っていうのはどこのどいつだい? …あたしだよ!」とご自身のギャグを披露し会場を笑いに包みました。
にしおかさんは2020年にご実家に戻ったことを機に、ご自身の母が初期のアルツハイマー型認知症であるとわかり、現在も“見守り”をされています。

「実家に戻って5年目で、母が認知症、姉がダウン症、父が酔っ払い、私が一発屋という家族構成です」(にしおかさん)
「忘れていることを思い出せない」「別人のような性格に変わる」など認知症の特徴
イベントでは、近藤先生にて認知症の症状についてのお話がありました。

「きっとみなさんが心配なのは、自分が認知症なのかどうか、ご家族が認知症なのかどうかということだと思います。認知症の症状としていちばん有名なのが、もの忘れですね。人とか場所が曖昧になってきて約束をまちがえてしまう。ちゃんと覚えていられないので、同じことを何回も聞いてしまうんです」(近藤先生)
誰でも人の名前が思い出せないなど、日常の中でもの忘れをした経験はあると思いますが、認知症を疑うポイントとしては、“忘れたこと自体を忘れている(思い出せない)”といった特徴。一般的な加齢によるもの忘れとの違いになると言います。
「それから、計画事などができなくなってきたりもします。計画というと大層なものに聞こえますが、意外と日常の中で問題なのはお料理。お料理という作業は計画する工程の集まりなのでお料理がじょうずにできなくなってしまうこともあるのです」(近藤先生)
ほかにも、認知症によって意欲の低下も起こります。意欲がなくなると、だんだん日付感覚もなくなってくると近藤先生。さらには、今までとは別人のような態度をとるようなこともあり、性格の変化が見られるのも特徴に挙げられます。

にしおかさんも実家に戻られた際、ご自身の母の変化に戸惑ったと話します。
「コロナ禍に入ったばかりの2020年に、実家がどうなっているかな、元気かなと思い戻ったんですよ。あわよくば母が料理を作ってくれないかなと思ったりもして。そうしたら、実家がちょっとしたゴミ屋敷みたいになっていて、母が座椅子の上にぽつんと座ってるんです。本当に部屋が散らかっていたから、掃除しようと声をかけたら『頭かち割って死んでやる!』って姉を連れて2階に上がってしまって。そんなネガティブなことを母が言うのを聞いたことなかったので本当にビックリしました。でも、本当に死んだらどうしようと追いかけてみると、寝ているんですよね。時間を空けて3~4回ぐらいくり返したときに『あれ?』と思って。もともと認知症の知識がほとんどなかったので、なにが起きているんだろうと思ったんです。
母が一家の大黒柱だったから、このままでは実家の暮らしが立ち行かなくなるなと思って、『私がいないよりいたほうがいいかな』と、そのまま実家に戻りました」(にしおかさん)
その後、精神科に母を連れていきCT検査をしたことによって軽度のアルツハイマー型認知症であると診断をされます。そこから約5年が経過した今、変化や症状の進行などはあるのでしょうか。
「母は元気ですけど忘れる頻度はすごく早くなりました。雑に言うと、4~5年前は30分か1時間ぐらい前のことがスコンと抜けて忘れてしまっていたのが、今は1ラリー会話をしたらそれも忘れっていうのが増えてきたかなと。あと、妄想も増えてきましたね。
でも、ずっととっていなかった要介護認定を最近とったら、『要介護1』だったんです。アルツハイマー初期って言われてから5年で、今『要介護1』なので、母もがんばっているんだなって思います」(にしおかさん)
「認知症の進行は個人差がありますし、もともとの性格も影響します。大黒柱だったにしおかさんのお母さまは、ルーチンを守る生活習慣というのがあったからこそ、生活が破綻しないのではないかと考えます。にしおかさんとの会話によるコミュニケーションもよい刺激になっていると思います」(近藤先生)
認知症を予防するためにできることは?
現在、認知症を確実に予防するための方法は確立されていません。ですが、生活習慣を規則正しいものに見直すことが有効になると近藤先生。具体的には、下記の6つのことを意識して整えていくとよいでしょう。
【食習慣】メタボリックシンドロームは認知症リスクを高める原因になる。
【運動】ウォーキングや筋トレなどの有酸素運動を行うと◎。
【コミュニケーション活動】社会的活動は海馬を萎縮させるストレス要因を低下。
【知的活動】趣味などを通じて知的好奇心を持ち続けると脳の健康維持につながる。
【質のいい睡眠】7~8時間の睡眠を確保し、体に合う寝具を選ぶ。
【生活環境】PM2.5など大気汚染は脳の炎症を引き起こすリスクが高まる。喫煙もNG。
また、認知症検査を行ってみるというのもひとつの手です。早期発見をすることで、認知機能の低下を遅れさせる可能性があります。Dクリニックが行う「アルツハイマー診断ドック」は、医師による問診のあと、頭部MRI/VSRAD検査を行います。最後に、腰部から脳脊髄液を採取し、アルツハイマー型認知症の原因のひとつであるアミロイド量の検査を行うことができます。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
イベントの最後には、にしおかさんがメッセージを残してくれました。
「今実家に戻っていますけど、それがいいとか悪いとかも思ってないですし、遠くから見守る方も、施設を選択する方も、自分で一生懸命考えた選択肢だと思うのでありだと思います。私は自分ファーストなのですが、とにかくみなさんも自分の元気と幸せを考えて、よりいい人生を歩んでいただきたいなと思います」(にしおかさん)
自分も大切に、家族も大切に。気づいた今このときから、“親子ウェルビーイング”を目指して過ごしたいものです。
文/FYTTE編集部