
11月1日の「紅茶の日」にあわせて、一般社団法人ウェルネス総合研究所がメディアセミナー「紅茶ポリフェノールの働き」を開催! 新たに発足した「紅茶ポリフェノールラボ」のとり組みが紹介され、ポリフェノール研究の第一人者たちが紅茶の健康・美容効果に迫りました。リラックスだけじゃない、紅茶の“可能性”に注目が集まったセミナーの模様をレポートします♪
Contents 目次
今、紅茶が“健康飲料”として再注目される理由
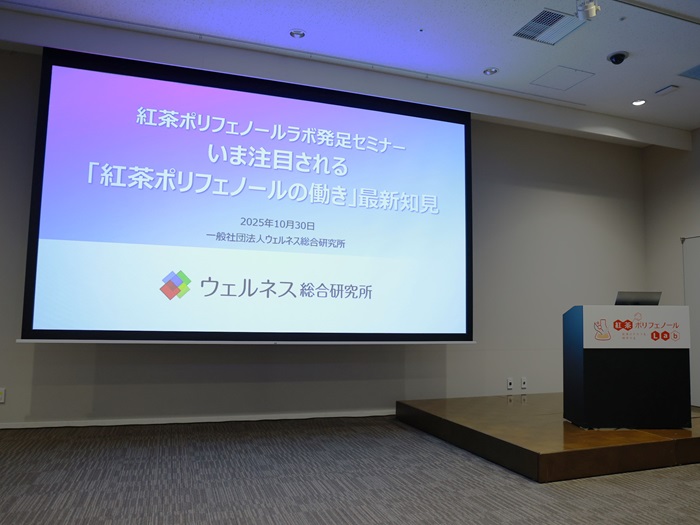
今、国内外で紅茶の人気が再び高まり、「第3次紅茶ブーム」とも呼ばれ、カフェや専門店には個性豊かな紅茶が並び、楽しみ方も多様に。紅茶といえばリラックス効果のイメージが強いですが、近年の研究では健康や美容を支える成分が豊富に含まれていることがわかってきました。
中でも注目されているのが、紅茶特有の「紅茶ポリフェノール」。
緑茶やウーロン茶とは異なる働きをもち、血糖値の上昇を抑制したり、脂質や糖質の吸収を穏やかにしたりする効果が報告されています。

セミナーの冒頭では、ウェルネス総合研究所 執行責任者 兼フェローの赤坂幸正さんが登壇。
「緑茶やウーロン茶の健康情報は多いのに、紅茶の情報はまだ少ない」と感じ、紅茶の機能に関する情報を啓発・発信するために今回の企画「紅茶ポリフェノールラボ」を発足したと語りました。
紅茶市場は年々拡大しており、健康志向の高まりとともにブームの波が訪れています。
11月1日の「紅茶の日」は、日本人が初めてロシアで紅茶を飲んだことに由来する記念日。赤坂さんは「このタイミングで、紅茶の最新研究を多くの方に知ってもらいたい」と話しました。
キレイと健康を守るポリフェノールの“抗酸化パワー”とは?

続いて登壇したのは、ポリフェノール研究の第1線で活躍されている農学博士、甲南女子大学 医療栄養学部 准教授の川畑球一先生。
「今 改めて注目されるポリフェノールの可能性」と題し、ポリフェノールの基本と最新の発見を紹介しました。
ポリフェノールは自然界に8,000種類以上存在するといわれ、代表的な働きは抗酸化作用。
呼吸によって体に入った酸素の一部が反応性の高い「活性酸素」となり、これが増えすぎると体をサビつかせる「酸化ストレス」(体が錆びる状態)の原因に。ポリフェノールはこの活性酸素を中和し、健康を守る助けをしてくれます。
さらに川畑先生は、ポリフェノールの働きを理解するうえで「腸内フローラ(腸内細菌叢)」との関わりがとても重要だと話します。
食事からとったポリフェノールのうち、体に吸収されるのはわずか約10%ほど。残りの約90%は大腸に届き、そこで約1,000種・100兆個以上ともいわれる腸内細菌と相互に作用します。
ポリフェノールは、菌の増殖を促したり抑えたりすることで腸内フローラのバランスを整える(ディスバイオシスの改善)効果があると確認されているほか、ポリフェノールをとることで、ビフィズス菌がオリゴ糖を利用して育つ働きがより活発になる可能性も示されており、今後の研究にも注目が集まっているとのこと。
また、腸内フローラはポリフェノールを分解し、より小さな分子に変化させます。こうして生まれた成分が、インスリンのように働いて血糖値のコントロールに関わる可能性もあり、今後の研究が期待されているのだそうです。
紅茶の赤いチカラ「テアフラビン」に注目!

次に登壇したのは、静岡県立大学 食品栄養科学部 客員教授の中山勉先生。お茶ポリフェノール研究の第一人者として、紅茶ポリフェノールの最新知見を紹介しました。
紅茶は発酵の過程で、カテキンがテアフラビンや、さらに複雑な構造を持つテアルビジンへと変化します。
じつは、この構造の“変化”こそが紅茶の機能性のカギ!
テアフラビンはカテキン類より分子量が大きく、その構造によって腸の細胞やウイルスなど、細胞の外側にある脂質膜(リン脂質膜)により強く作用します。
こうした性質は緑茶に含まれるカテキン類にも見られますが、テアフラビン類はその力がさらに強く、少ない量でも膜にしっかり結びつくことが実験で明らかになっています。
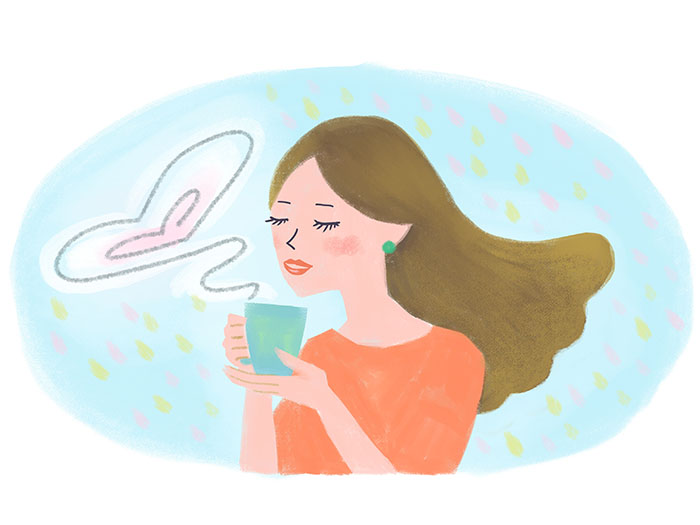
また、吸収される量はごくわずか(0.01%以下)ですが、それにもかかわらず、紅茶ポリフェノールにはさまざまな健康効果が報告されています。
中山先生は、紅茶ポリフェノールの健康効果の多くが、体内に吸収される前の腸管内で起こる物理的な相互作用によって説明できると話しました。
1. 脂質の吸収をおだやかにする
食事でとった脂質が腸の中で細かく混ざり合った“乳化”という状態を解除し、脂質やコレステロールの吸収を抑える働きがあります。
その結果、血中の悪玉(LDL)コレステロール値を下げる効果が、動物実験やヒトを対象にした研究でも確認されています。
2. ウイルスの働きを抑える
インフルエンザウイルスやコロナウイルスに対して不活化作用を持つことが報告されています。紅茶の成分がウイルスの膜に作用し、増殖をストップさせると考えられており、緑茶のカテキンよりも強い効果を示すというデータもあります。
3. 血流をサポートする
テアフラビンを摂取すると、動脈の血流が増加する現象が報告されており、これは吸収を前提とした現象では説明しづらく、腸管細胞に作用したテアフラビンが神経を介して脳に情報が伝わり、血管拡張を促している可能性があります。
英国研究で判明! 紅茶で“死亡リスク低下”の可能性も
さらに中山先生は、イギリスで行われた大規模な追跡調査の結果を紹介し、1日2杯以上紅茶を飲む人は、飲まない人に比べて血管疾患や虚血性心疾患、脳卒中などの死亡率が低下したというデータが示されました。
この効果はカフェインによるものではなく、紅茶特有のポリフェノールによる健康作用と考えられているとのこと。
中山先生は「紅茶ポリフェノールは、脂質膜への高い親和性を活かし、細胞やウイルス、消化酵素などにくっつき個々のメカニズムに応じて多様な生理作用に発展していると考えられます」と語りました。
ウェルネス総合研究所が立ち上げた「紅茶ポリフェノールラボ」では、今後も紅茶の魅力を科学的に発信していくとのこと!
日々の健康や美容のために、改めて紅茶を生活にとり入れてみてはいかがでしょうか? “ほっとひと息”の時間が、未来の健康につながるかもしれません♪
取材・文/FYTTE編集部





